=2=
五年前。
初めての帰郷はローリー−セオドア=ローレンスの大学の卒業祝いと重なった、
とても素晴らしい日となった。
その日はマーチ家でもローレンス家でも笑い声が絶える事はなく、
その頃から少しずつ身体の調子を崩し始めていたベスも声を立てて笑った。
ジョオはそれが嬉しかった。
その帰り道、ジョオはもう古くなった”ローリーのポスト”に
自分宛の手紙が入っていることに気付いた。
短いその手紙にはローリーの筆跡で”明日会って話したいことがある”とだけ書かれてあった。
いつものローリーらしくない手紙に何故かジョオは胸騒ぎを覚え、
その夜はなかなか寝就くことができなかった。
そして次の日、ジョオは時間より早めに約束の場所へと急いだ。
ローレンス邸近くの湖畔、よくボート遊びをしたあの場所で
ジョオは彼が来るのを一人待った。
いちょうの葉は既に色づき、時折吹く風も冷たい。
ジョオが冬の訪れを予感した時、並木道の向こうにローリーの姿が見えた。

自分の手より一回りも大きいその手に、
ジョオは目の前にいる存在が最早自分の知っている少年ではないことを悟った。
「‥ずっと君が好きだった。」
ローリーは続けた。
「あの窓辺で出会った時から、ずっと。
君がニューヨークへ行っている時も君の…君とのことを思い出さない日は無かった。」
ローリーの漆黒の瞳はまっすぐにジョオを見つめている。
「今までもそうだった、ずっと。
でも、君はそれを聞かせてくれなかった。
だが今日こそは聞かせて欲しいんだ。君の気持ちを。」
ジョオは恐れていた瞬間が来たことを知り、自分の表情が徐々に哀しみに強張っていくのを感じた。
ローリーはじっとジョオの表情の変化を知りながらそれでも続けた。
「僕と結婚して欲しい。」
秋の風が遥か高い場所でごうごうとうねっているのが感じられた。
まるで自分たちの時間だけが止まっているような感覚。
足元に落ちた帽子を取る事もできずにジョオはその凍りついた時間の中にいた。
想い出が嵐のように心の中を駆け巡っていく。
私の一番大切な親友、その人は今、心の中から零れ落ちようとしている。
「……ローリー。」
ジョオはローリーの熱情から身を守るかのように背を向けた。
空気は鋭さを増し、刃のように次々と二人の心を傷つけていく。
ローリーもまた耐え難い苦痛の中にいるのだろう。
ジョオは一層、表情をゆがめた。
その顔を見られていないのだけが救いだった。

「・・それが答えかい?。」
ローリーの反応は打って変わって冷ややかになった。
「ち、違うのよ、ローリー。
私はあなたにそんな風に私を想って欲しくなかっただけ。
だって、私はまだ作家として何一つ達成してないのよ。
それに私は誰とも結婚なんかするつもりは‥ないわ」
本当の気持ちだった。
いや、3年の時間の中でいつしかローリーに追い抜かれていた自分が
恥ずかしかっただけなのかもしれない。
しかし、ローリーの声色はみるみるうちに手負いの獅子のように
死の淵の怒りをはらんでいった。
「そんなのは良い訳だよ、ジョオ!
だって君はまた彼のいるニューヨークへ行くんだろう!
僕は君がニューヨークへ行ったその時から分かっていたさ!
君はどういう気持ちか、何故我が家を捨てたのか・・・」
そこまで言った後、ローリーはジョオの涙に震える肩に気付いてようやくハッとなった。
ローリーの口から放たれた激情は裏切りの刃となってジョオの心に突き刺さった。
「…やめて!」
ジョオは叫んだ。それはもう涙に震えた、搾り出すような心の叫びだった。
ジョオは目をぎゅっとつむった、頬を一筋の冷たいものが伝うのを感じる。

私の心の中にはいつも陽だまりのような場所があった。
それはニューヨークでの孤独な生活の支えになり、
想像の翼を伸ばせば、いつでもあの頃の私に戻ることができた。
そんな私の心の一部、大切な若草の想い出……。
ジョオは震える声を、必至に押さえつけながら言った。
「ローリー、あなたは今も……これからも大切な友達。
でも、あなた、あなたが私に言うように…、」
ジョオは、涙で声が詰まらせながら声を振り絞った。
「あなたのことを愛することは出来ない……出来ないの。」
長い、長い沈黙の果てにローリーは問うた。
「…本当にそう?」
故郷を流れ過ぎ去っていく冷たい風。
ここに吹いたと思ったらもう遥かかなたへ消えていく。
私もまたここから消え去らなくてはいけない。
「……本当にそうよ…。」
最早、背中にあのローリーの熱は感じられなくなっていた。
彼は落ちていたジョオの帽子を拾うと振り向いて言った。

「…分かった、気にしないで。」
しかし、言葉に反してローリーの顔はまるで彫像のように冷たく感じられた。
そして彼はもう二度と振り返ることなく、来た道を引き返して行った。
ローリーの手渡してくれた帽子もひんやりと冷たかった。
ジョオはそれをぼんやりと見つめながら、
まるでローリーが彼の心を捨て去って行ったかのように絶えがたい寂しさを感じていた。
その時から5年・・ジョオとローリーが会うことはついになかった。
再び、一際大きな汽笛が鳴り、ジョオは我に返った。
いつしか老婦人は向かいの席でうたた寝していた。
窓の外を見ると遥か遠くにニューコードの街並みが見え始めている。
ジョオは帽子が飛び去った彼方を見つめながら空に向かって何かを呟いた。
しかし、彼女の言葉は汽笛の音にかき消され、
故郷から吹く風の中に散っていくのだった。
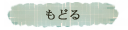
「大学合格、本当におめでとう。」
ジョオの固い笑顔にローリーは一瞬の沈黙を見せてありがとうとだけ言った。
「・・驚いたのよ、3年の間ローリーもずっと勉強を頑張っていたのね。」
ジョオは努めて明るい声で続けた。
「これからは少しゆっくりしなくっちゃね。」
「…ジョオ。」
ローリーは真剣な表情でジョオの言葉を遮った。
その瞬間、強い風が吹いてジョオの帽子を秋の空へと舞い上げた。
ジョオにはその風がまるでローリーの心の隙間から溢れ出した情熱の波動のようにも感じられ、
いよいよ胸の鼓動が激しく打ち続けた。
「……お願い、言わないで!」
ジョオの口を突いて出た言葉はそれだった。
「何も聞く前からそう言うんだね。」
そして一瞬の決意の沈黙の後、ジョオの手に触れた。






